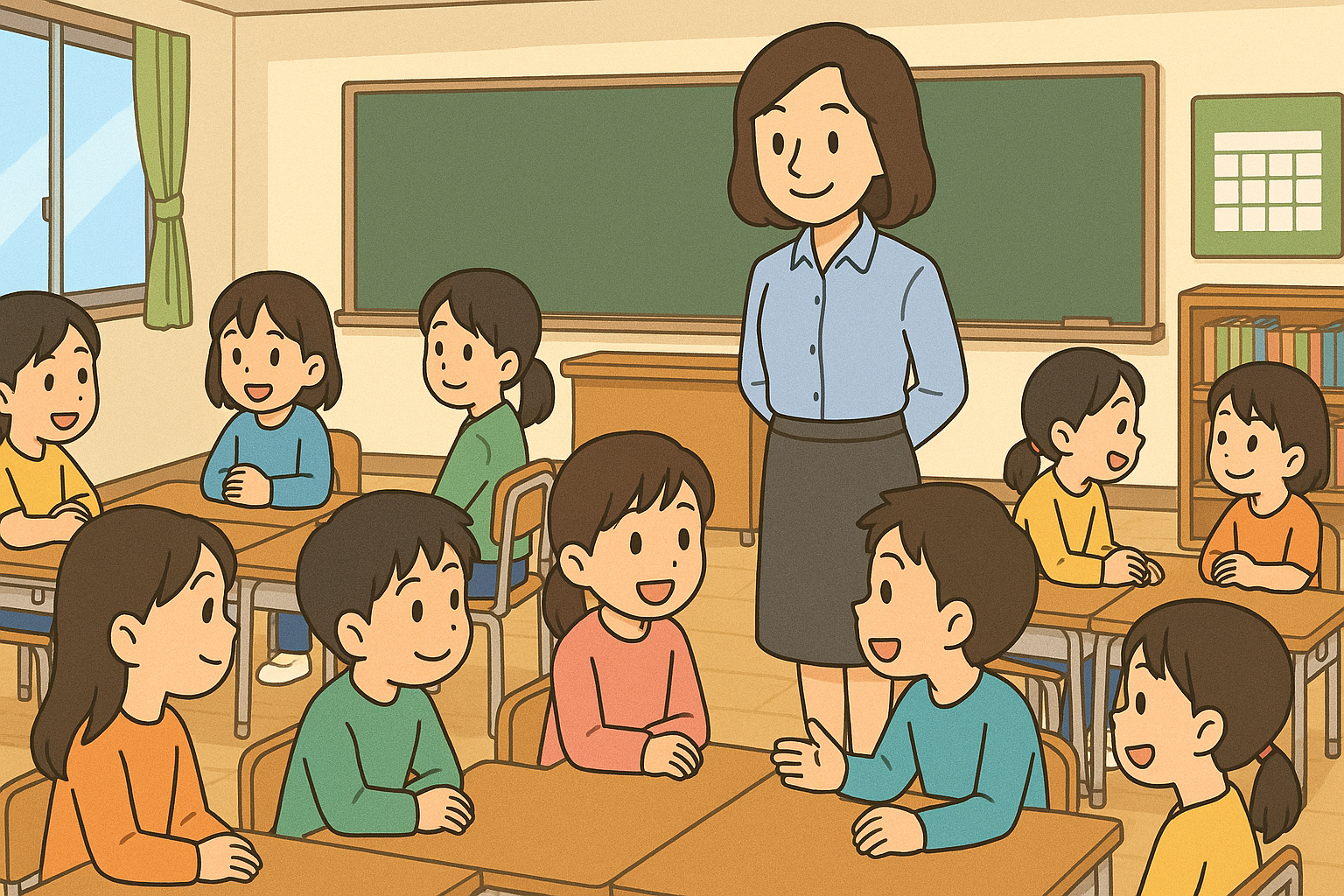『生きる力』を育むために
元小学校教諭・田中希望先生
モンドAIで主体的な学びを
13年間、小学校の教員として現場で働いてきました。辞めたのは、「自分の目で本物のモナリザが見たいから」という理由からでした。そんな私が現場で感じたことを踏まえながら「モンドAI」についてお伝えできればと思います。
まず、改訂された新学習指導要領について簡単に触れます。小学校は2020年に改訂されました。なぜ改訂されたのかというと、これからどんどん変化していく激しい時代に合わせていける人を育てていくためです。
関心・意欲・態度で評価するのではなく、「生きる力」を育みグローバルな社会に対応できる資質・能力を!というものでした。しかし、ねらいを提示されても、担任として何ができるのか、どうしたら「生きる力」が育つのか。当時は日々もやもやと葛藤していました。
【主体的な学び】
たどり着いたのは、どのように学ぶかという問いから答えへ行き着くまでの過程の大切さです。「1+1=2」とすぐ教えるのではなく、お金で置き換えてみたり食べ物で考えてみたりと、具体性をもって答えを導き出します。答えは「2」なのですが、その過程が一人ひとり異なり、その異なった経緯こそが粘り強く繰り返し学ぶ姿へと繋がっていきます。
【対話】
先ほど学びの過程の大切さについて触れましたが、どうしてもそのためには「対話」が不可欠となります。ペア活動やグループ活動を通し、他者の考えを聞き合うことで知識理解を深めるだけでなく定着へと繋がりました。しかし、それは実際はうまくいった場合の話です。相手はお互い小学生。聞いて!聞いて!の場合もあれば、言いたくない、分からない、という場合も多々あります。アウトプットをするだけでは、効果は半減です。ですから、教師が間に入り話を深めるような問いかけをする必要があります。教室中にできた話し合いのグループそれぞれに入っていき、適切なタイミングでアドバイスや問いかけをするというのは至難の技です。このように、「対話」の大切さは実感していても限界があることを感じていました。
【深い学び】
これらの課題を解決してくれる画期的なソフトが「モンドAI」です。実際に使ってみて良かった点を2つまとめました。
① 主体的な学びにつながる仕組み
さまざまな問いに対して、モンドAIは驚くほど寄り添って答えてくれます。他のAIは、すぐに答えを出すので、一問一答型が多いです。しかし、モンドAIは「なぜだと思う?」と問答式です。過程を大事にしたこのやりとりこそが、主体的な学びに繋がっていきます。粘り強さが身につくことで、深い学びとなります。やり取りの中で好奇心を刺激されることで、記憶にも残るだろうなと感じました。
② 続けていける仕組み
はじめは目新しさで取り組んでみたものの、続かないことがあるかもしれません。しかし、モンドAIならAI通知表を通して家族との対話が生まれます。見てもらえているという感覚は、何より子どもの安心につながります。褒められたから続ける、ということではなく、やはりAIはツールの一つとして捉え、最終的には家族など大人と繋がることで続けていくことができるのではないでしょうか。続けていくことが、深い学びに繋がっていきます。
これから各家庭でぜひモンドAIを使うことで、「生きる力」という深い学びを身につけていくことができると感じました。しかし、元教員としては、一番は教育現場で使用してもらいたいなと強く願います。調べてそのままコピペをして書くのではなく、自分の考えを引き出しながら答えへと結びつけていくことの大切さは、教員なら誰もが分かっています。活用し、続けていくことで考える癖がつくのではないでしょうか。
私が「本物のモナリザを見たい」と感じたように。一問一答ではすぐ消えてしまう興味や関心の小さな炎が、ずっと消えず心に残っているような。そんな未来が訪れるような学びを積み重ねていってほしいと子どもたちには願っています。