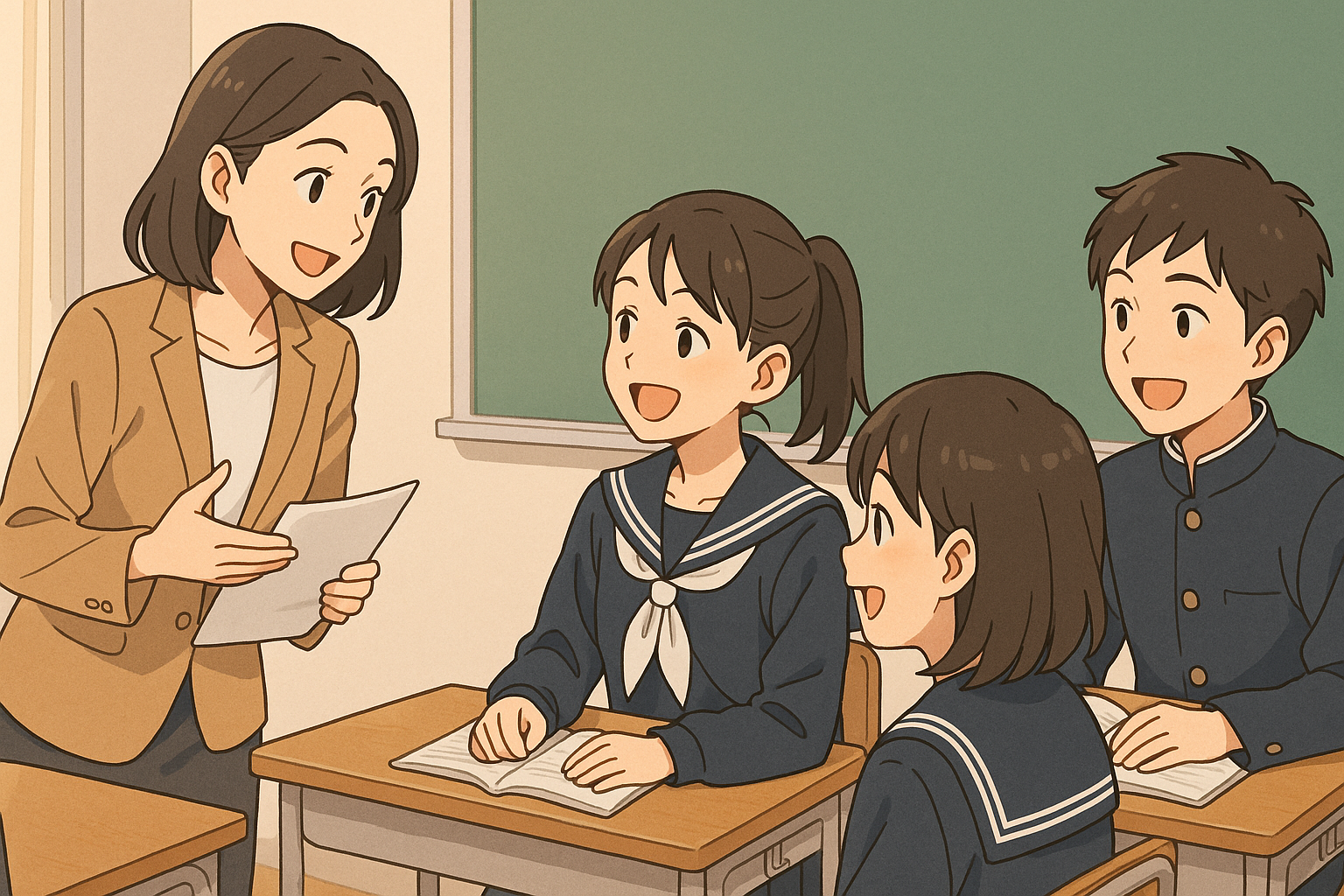対話型AIによる個別学習支援への期待
元中学校教諭・武井玲奈先生
AIの急速な身近化と教育現場への浸透
AIは従来、遠い未来の技術として捉えられてきましたが、今や私たちの日常生活に深く浸透し、教育分野においてもその活用が急速に進んでいます。特にAIとの対話は、相手との関係性や時間的制約、内容の制限を気にすることなく自由に行えるという特性があり、これらの利点は対話型授業を推進する現代の教育現場が抱える様々な課題を解決する可能性を秘めています。
理想的な対話型授業とその限界
私が教育現場で勤務していた際は、授業の中で必ず対話の時間を設けることを心がけていました。授業冒頭に投げかける発問や、生徒から自然に湧き上がる疑問を出発点として、生徒が主体的に謎を解き明かしていく時間です。この過程で生徒たちは、これまで培ってきた知識を最大限に活用し、疑問の解決に取り組みます。教師が一方的に答えを提示したり、解決方法を説明したり、問題演習を繰り返させるのではなく、生徒自身が主体的に思考し、対話する力を育成することを目標としていました。
しかし、このような理想的な学習活動に参加できない生徒も少なからず存在します。基礎知識が定着しておらず発言に自信を持てずに沈黙してしまう生徒、クラス内のコミュニティに馴染めず対話に参加できない生徒、発問を自分事として捉えられず主体的な参加が困難な生徒などです。これらは一斉授業形態の構造的な課題であり、教師としても自身の指導力不足を痛感する部分でもありました。
生徒の興味関心をいかに引き出すか、魅力的な授業を通じて生徒間の良好な人間関係をいかに構築するか、必要な知識をいかに確実に定着させるかという問題は、常に私の頭を悩ませ続けていました。
「モンド AI」との出会いがもたらした衝撃
このような状況の中で対話型AI「モンド AI」を実際に使用する機会を得て、従来の教育に対する常識が根底から覆される体験をしました。授業中に上手く発言できない生徒や、他の生徒や教員のペースについていくことが困難な児童生徒にこそ、このAIを活用していただきたいと強く感じています。
AIとの対話が生み出す新たな学習体験
AIとのチャットでは、まず疑問に思っていることをAIに送信します。例えば「月食って何?」という素朴な疑問を投げかけてみました。「こんなことを知らないなんて恥ずかしい」といった心理的な負担を感じる必要がないのが、AIの大きな利点の一つです。
するとAIは次のように応答してくれました。「月食について知りたいんだね。月食は、月があるものに隠されてしまうときに起きるんだよ。さて、月は何のまわりを回っているか覚えてる?」この応答に私は深い感動を覚えました。一般的なAIであれば「月食とは…」と即座に答えを提示してしまうところですが、「モンド AI」は答えをすぐには教えず、これまでの知識を活用して自ら答えを導き出せるよう支援してくれます。まさに真の対話を体験している感覚で利用することができるのです。
AIからの質問に「地球」と答えると、「そうだね、地球の影の中に月が入るんだよ。じゃあ、地球の影に入った月は、空でどんなふうに見えると思う?」と再び問いかけてくれました。この応答にも深い感銘を受けました。最初の疑問である「月食って何?」の理解が深まった上で、そこから派生する興味深い新たな疑問を提示してくれたのです。
「真っ暗になる」と私が答えると、「実は赤っぽく見えることがあるんだ。なぜ赤く見えるか、どんな理由があると思う?」と、次々に新しい知識の広がりと思考の深化を促してくれます。
主体的学習への扉を開く可能性
このように、小さくて素朴な疑問から始まった対話が新たな深まりを見せ始めました。子どもたちも勉強中にふと疑問に思ったことをAIに投げかけたら、きっと夢中になって学習に取り組むことでしょう。それは授業中の誰かの発言によって決められたテーマや教師が設定した発問ではなく、自らの頭の中から自然に湧き上がった疑問から始まる対話だからこそ実現するのです。
主体的な学習に取り組むためには、そのきっかけが極めて重要です。「モンド AI」は、子どもたち自身がどのようなことに興味を持ち、何を知りたいと考えているのかを発見する貴重な機会にもなり得ると考えています。
すべての子どもたちに開かれた学習支援
学校の環境、クラスの雰囲気、人数構成、座席配置、教師との相性など、教育を取り巻く環境には様々な差異が存在します。しかし、授業中の対話に何らかの不安や困難を感じている児童生徒にとって、対話型AIは新たな学習の扉を開く可能性を秘めた強力なツールとして、心からおすすめしたいと思います。